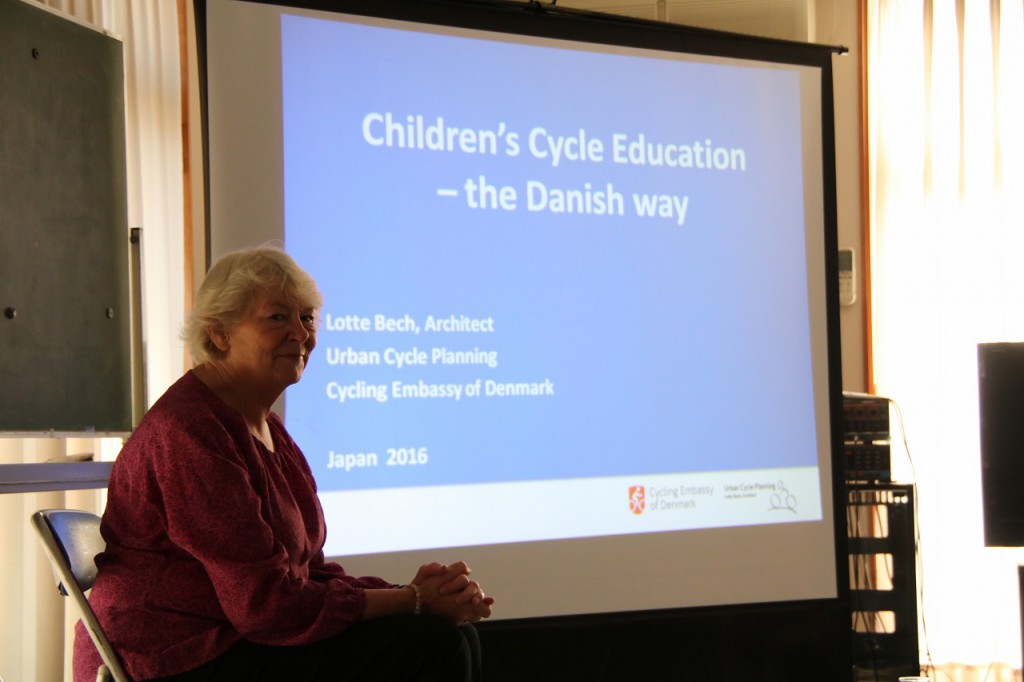体験!デンマーク式自転車教室♪【後編】
人とまちをつなぐコミュニケーションツール。
金沢レンタサイクルまちのり。
今回は、昨日お届けしたデンマーク式自転車教室の後編をお届けします。前編については、ぜひ昨日のブログをご覧くださいませ!
▼少し復習をかねて。10/16(日)午前中にデンマーク式の自転車教室が開催されました。日本海側初の試み。講師は、デンマークサイクリング大使館のロッテ・ベックさん。総合司会&通訳は三国千秋先生。23名の子どもたちが参加。年代別に3グループに分かれて、デンマークで実際に取り組まれている「サイクリングゲーム」に挑戦。楽しく自転車の乗り方や体の使い方を学びました。
午前中のサイクリングゲームのあと、場所を湖陽町民会館に移し、ロッテさんによる講演が行われました。講演のお題は「Children’s Cycle Education – the Danish way」(子どもたちの自転車教育-デンマークの方法)です。
▼ロッテさんの講演の様子。
▼身振り手振りを交えて熱く語るロッテさん。
▼ここでも通訳&進行役を務めていただいた三国千秋先生。
とても興味深い講演の内容をすべてご紹介することができず残念ですが、多くの示唆を得ることができました。今回は文章がメインとなりますが、ロッテさんの講演で印象に残ったフレーズやキーワードを5つにまとめてご紹介したいと思います。
1.自転車利用者の割合は脅威の45%!
自転車先進都市として世界的に有名なデンマークのコペンハーゲンでは、通勤・通学時の自転車利用者の割合はなんと45%!わが国では大阪市が30%程度で日本一となっており、これでも十分高い割合ですが、なんとその1.5倍もの割合を占めています。ちなみに公共交通利用者は27%、自動車23%、徒歩5%とのこと(2014年)。交通手段で最も利用されているのが自転車なのです。
これはなぜか。
デンマークをはじめとする欧州諸都市では、酸性雨の問題や温暖化による海面上昇の影響が顕著に出ていることもあり、国や都市を挙げて環境保全に取り組んでいます。コペンハーゲン市も1960~1970年代は日本と同じくクルマ中心だったとのことですが、その後の自転車利用促進により、年間約90,000トンの二酸化炭素削減に寄与しているとのこと。また、健康への貢献度も高く、通勤する大人の死亡率が30%低下したとの統計もあるそうです。
こういった環境面や健康面における自転車の効果を都市環境の改善にも活かすべく、自転車通行空間の整備や子どもたちへの自転車教室などの幅広い自転車施策を強力に推進しているため、45%という凄まじい割合を占めることになったようです。国や自治体、警察、市民など幅広い主体間の連携と、ハード・ソフトの両輪での対応が重要ということに改めて気づかされました。
2.自転車教育は小さいころから始めるのがポイント!
都市環境や人生を大きく変える力をもつ自転車。
デンマークでは、自転車をしっかりと適切に利用してもらうための取り組みを国レベルで率先して実施しています。その一環が、今回金沢でも実施していただいた子どもたちを対象とする「Cycling games」です。
ロッテさんいわく、小さいころに自転車の楽しさや乗り方を教わった人のほとんどが、大人になっても自転車を利用するとのこと。できるだけ小さいころから慣れ親しむことが大切とのお話でした。
具体的には、子どもが2~3歳のころから自転車教育をスタートし、小学校には交通教育を専門とする教員を配置。8~9歳のときには自転車免許証を取得。12歳になると公道を使用して交通ルールを学び、免許証よりもグレードの高いサイクリストのライセンスを取得し、公道を一人で運転できるようになることが目標となっています。
一方、日本の場合はどうでしょうか?
金沢市では市内全小学校の3年生に、交通公園での自転車講習会を実施しており、全国的にも手厚く実施しているほうかと思います。が、それ以外に学ぶ機会はありませんし、法的にもそのような規定はありません。よく考えてみると、交通行動に関する知識や理解が何もないまま自転車に乗っている(子どもに好き勝手に乗せている)というのはちょっと怖い気がしますね。このことが結果的に自転車関連事故の増加や、自転車や歩行者に配慮のないドライバーの増加につながってしまっているのかなと感じます。
3.Keep it simple, Make it FUN !
上記で触れたように、2~3歳から自転車教育に取り組むデンマークにおいては、小さな子どもでもわかるように、次の2点を重視しているとのことでした。
Keep it simple (とにかくシンプルに)
Make it FUN (とにかく楽しく)
これらは当たり前のようにも聞こえますが、頭の固い大人にとってはとても難しいことであり、極めて重要なキーワードだと感じました。この2つの考え方から、昨日のブログでご紹介した「シャボン玉ゲーム」や「ストップ・オン・ザ・リング」、「洗濯物干しゲーム」、「ボールゲーム」などのユニークでわかりやすいプログラムが出来ているんだなと理解できました。
さらに、この2つのキーワードは、日々の仕事や生活をしていく上でも大切にしていきたい言葉であり、純粋に、遊び心をもって人生を豊かにしていきたいなと感じました。座右の銘にしたいと思います。
4.自転車と教育プログラムを統合的に展開!
デンマークの20,000人の子どもたちを対象に行われた調査結果によると、自転車や徒歩で通学する子どもたちは、集中力や学習能力が高いという結果が出ているようです(おそらくクルマで送迎してもらう子どもとの比較)。このことから、デンマークでは通学前の45分以上の運動が法律で推奨されているようです。
この観点からも、自転車の有用性が認められており、自転車は様々な教育プログラムに統合されているようです。
たとえば、サイクリングは自然や科学技術、スポーツの授業への応用。また地球一周が40,000kmであることを活かし、デンマークから何キロ走ればどこの国にたどり着くかという地理の授業とのコラボレーションなどが挙げられていました。
以前のブログで紹介したバルセロナの事例では、バスやトラム、自転車などの公共交通サービスを統合的に提供することの重要性を指摘しましたが、今回のロッテさんのお話からは、自転車と教育をうまく統合していくことの重要性を学ぶことができました。ここでも「integrate」という言葉が重要なキーワードとなりました。
5.自転車を通じて、子どもの自尊心を育む!
最後にご紹介したいのは、今回、金沢で実施していただいた「Cycling games」の真の目的です。
ロッテさんのお話の中で、「Why cycling games?」というスライドがありました。そこには、大きく2点の記載がありました。
①自転車を通じて子どもの発達を助ける(体力、運動能力、精神、認知能力の4つの観点から)
②サイクリングを通じて、社会活動の一翼を担い、喜びを感じ、自尊心を育む
この中で、僕が最も感銘を受けたのは、「Build up the child’s self esteem」(子どもの自尊心を育む)というフレーズです。
実際に「Cycling games」を体験した僕なりの解釈では、自転車に乗るという成功体験を通じて子どもたちに自信の種を植え、自ら学び体験することの楽しさや尊さを感じる心を育む、ということかなと思います。
日本語で「教育」と訳されるeducationは、educe(可能性を引き出す)という言葉が語源といいます。このことから、福沢諭吉先生は「発育」と訳すべきと指摘したとの話もあるようです。
「教育」というと、大人が子どもに教えて育てるという意味合いが強く感じられますが、「発育」というと、子どもが自ら育つ力を引き出していくという方向性が感じ取れます。
まさにデンマークの「Cycling games」は、日本でいう教育ではなく、子どもが自ら育とうとする力を、自転車という乗り物を活かして最大限に引き出すプログラムであるように感じました。
ちなみに、デンマークで「Cycling Education」(自転車教育)を始めたのが1942年。なんと74年もの歴史を有しています。かたや日本では、ようやくその考え方が少しずつ普及してきているというところであり、まだスタートラインにも立てていないという印象です。
本当の意味でスタートラインに立つためには、今回の「Cycling games」をイベント的に終わらせるのではなく、幼少期からの発達プログラムとして保育園や小学校のカリキュラムに組み込み、その必要性を交通法規の中でも明確に位置づけるなど、教育制度や法体系を含めた根本的な改革が必要であるように感じます。
道のりは遠いですが、自転車の安全利用という単焦点的な考え方ではなく、「自転車を活かした子どもの発育支援」という広い視野をもって、日本そして金沢での今後の展開を考えていきたいと思います。
以上、ロッテさんのご講演からいただいた気づきでした。今回の経験を機にデンマークの考え方に学びながら、少しずつ実践につなげていければと思います。
ではまた。